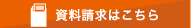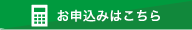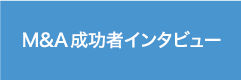有限会社竜乃家
“業績好調”の鹿児島和菓子メーカーが事業承継で選んだ地元の大企業
| 譲渡企業 | 譲受企業 |
|---|---|
| ㈲竜乃家 | ㈱西原商会 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 郷土菓子製造 | 業務用食品卸 |
| スキーム 株式譲渡 | |

鹿児島県鹿児島市にある有限会社竜乃家(たつのや)は、和菓子の製造・卸売・小売を手掛けています。前社長で顧問の二見竜生氏(60)は伝統的な和菓子に改良を加え、ヒット商品を生み出してきました。
事業は好調でしたが、後継者がいないことや、会社の成長に限界があると考え、2025年1月、地元の大手企業である株式会社西原商会(本社:鹿児島市)へ株式譲渡をしました。M&Aに至るまでの経緯や、譲渡後の現在の心境について二見社長にお伺いました。
メーカー勤務を辞めて経営難の家業に
創業は1976年と50年近い歴史があります。
父が脱サラをして退職金を元手に「滝ノ神茶屋」という屋号で創業しました。そして姶良郡加治木町(あいらぐんかじきちょう)(現・姶良市)で、江戸時代中期から作られている郷土菓子「加治木饅頭」の製造販売を始めたのです。小さく分けてフィルムで包んだ「ミニ加治木饅頭」を開発し、大手スーパーなどで販売を伸ばしました。
伝統的な和菓子をアレンジしてヒット商品にしたのですね。
商品を発泡スチロールに入れて冷まさずに売ることで、温かくできたての味わいを提供していました。地元の大手小売店では、単品の商品として販売がトップになったこともあります。1982年に店舗兼工場を建設して創業時のプレハブ小屋から移転したのを機に、まんじゅうを自動で包む製造設備を導入して、生産数を伸ばしていきました。これが現在も稼働している店舗兼工場です。
二見さんが家業を継いだ経緯を教えて下さい。
好調に伸びていたスーパーでの販売も徐々に頭打ちとなり、工場への投資が重荷になっていました。そして母が体調を崩したことも加わり、経営の存続が難しくなった一方で、高速道路のサービスエリア(SA)で商品が売れ始めるなど、やり方によっては再び成長できる芽もありました。
ちょうど、私が大学卒業後に神奈川県のOA機器メーカーに就職し、設計の仕事をしていた32才のころのことです。家業の経営難を受けて、会社を辞めて家業を継ぐことを決心しました。Uターンした1995年に屋号を現在の「竜乃家」に変更しています。よく使われる「屋」ではなく「家」にしたのは、家を守りたいという思いがあったからです。
伝統的な和菓子屋の経営を改革
最初にどのようなことから着手したのでしょうか。
先に家業を手伝っていた妹と一緒に、掃除などを率先してやりました。私はメーカーの会社員だったので、経営はまったくの素人です。和菓子の作り方も知りませんでした。
むしろ、早朝3~4時から働いていた父の背中を見て、「この仕事はやりたくないな」と思っていたくらいです。そんな私ができることは、従業員にやる気のある姿を見せることでした。とにかく手探りで、やれることは何でもしました。
その後に商品の拡充をしていますね。
SAで加治木饅頭の実演販売などをして売上を伸ばしていたところ、ある人から言われた言葉に目が覚めました。「いつまでも同じことをやっていたらダメだよ」と。昔ながらの製法で加治木饅頭を作ることしかしておらず、気が抜けていた面があり、このままではいけないと、将来を見据えて商品の幅を増やすことを決めました。
そこから、いまの主力商品に育った九州沖縄の郷土菓子「かるかん」や、鹿児島県の郷土菓子「いこもち」を作るようになりました。
開発では、どのような工夫をしたのでしょうか。
「かるかん」は山芋・米粉・砂糖が原材料です。山芋の価格が高いため、従来通りの配合バランスで作ると、製造コストが膨らんでしまっていました。何とかできないかと、配合の条件をさまざまに変えながらトライ&エラーを繰り返し、米粉や水の比率を高めて、山芋を減らしても食感が損なわれないギリギリの配合を追及しました。私がメーカー勤務でやっていた機械のトラブル対策などの経験がここで役に立ったのです。
また、「かるかん」は羊羹のような直方体に成形して小分けにカットするのですが、そのやり方だと熟練の技が必要になります。それを最初に平べったい形にしてからカットする製法に変え、熟練者でなくても誰でもカットできるようにしました。
これらの施策によって1個当たりの製造コストを20~30%減らし、低価格での販売を実現したわけです。雑誌で取り上げられた効果もあって、県内外で売り上げを伸ばすことができました。
縮小するかM&Aをするかの二択
経営が好調にもかかわらず、M&Aに踏み切ったのはなぜでしょうか。
私が60才となり、体調面で無理ができなくなったほか、スタッフにも多忙な業務で負担をかけていました。さらに、先代のころから稼働させている工場のキャパも限界が来ていました。このまま事業を続ける場合、縮小するかM&Aをするか、二択しかないと思ったのです。せっかくお客さまに喜ばれる商品がありますし、取引先もたくさんあります。
縮小するのはもったいないと考え、M&Aを決意しました。
インテグループを選んだ理由を教えてください。
最初に銀行と商工会議所に相談に行き、譲渡先探しを始めてもらいました。その後、2024年2月にインテグループの岡部(航大)さんからダイレクトメールをいただきました。
日々、たくさんのメールが来るので正直、面倒だと思っていたのですが、その時はなぜかわかりませんが、返信したのです。
それまでM&A仲介業者にはあまり良いイメージがなかったのですが、岡部さんに実際に会って話をしてみると、誠実さと信念を持った方だと感じて、M&Aをお願いすることにしました。
譲渡先の選定はどのようにしましたか。
岡部さんから、「西原商会さんにお声がけしてみましょう」と言われました。業務用食品卸大手の西原商会は鹿児島市だけでなく、全国的に大きな企業です。これまで多くのM&Aに成功していて、私も真っ先に頭に浮かぶ企業でした。
ただ、売上高1,200億円を超える企業で、うちのような規模では相手にされるはずがないと考えていましたし、銀行と打合せしていてもお話はでてきておりませんでした。その西原商会に岡部さんから打診してもらい、1カ月ほどでトップ会談が実現したのです。「まさか」という思いでした。
ダメもとで打診した本命からオファー
そこから譲渡に至るまでの経緯を教えてください。
トップ面談では、西原商会の西原一将社長に当社の歴史をひと通り説明して、「郷土菓子の文化を残したい」という思いを伝えました。その2週間後、具体的な金額まで書かれたM&Aの基本合意書が届いたのです。あまりのスピード感にびっくりしましたね。そこからDD(デューデリジェンス)が始まり、無事に2025年1月に譲渡を終えることができました。
譲渡を終えた現在、どのようなお気持ちですか?
相手にされないと思っていた企業ですから、託したあとの心配はありません。地元の大きな企業ですし、当社に不足していた人材を投入してもらえます。今は生産拠点の移設、新商品の開発、販路の拡大といった話があり、譲渡からまだ1カ月程度ですが、急ピッチで物事が動き出しています。私は竜乃家の社長から顧問になり、引き続き事業に携わっていますが、今後の不安はまったくなく、楽しみしかありません。
従業員たちの反応はいかがでしょうか。
M&Aの活動自体は2年程前から行っており、主力の従業員にはそのころからM&Aの可能性については伝えておりましたが、お相手が西原商会さん知った時には、みんなびっくりしていましたね。また、雇用はすべて引き継いでいただく契約になっていて、大企業に就職することになるのでみんなには安心してもらっています。
私が商品の注文を取りすぎて従業員の業務過多になっていた部分もあったので、西原商会の傘下に入ることで、ようやく労務環境を改善できると考えています。
「業績がどん底のときには買い手は現れない」
業績が好調な時期の売却が奏功したのでしょうか。
60才での譲渡について、「早すぎるのでは」と言われることがあります。ただ、私自身が株式投資をするのでわかりますが、業績がどん底のときには買い手は現れません。現れたとしても希望の金額が出てくることはありません。上り調子で成長が続いているときであれば、魅力的な企業に手を上げてもらえます。
当社はDDが始まったあとも東京ビッグサイト(東京国際展示場)のイベントに出展し、大手スーパーなど新規の販売先を獲得しています。そうした好材料があったこともM&Aがスムーズに進んだ要因になっていると思います。
M&Aを通じて苦労した点は?
DDでは税理士や弁護士などのインタビューを受け、 10年以上前にさかのぼって会社の決算や財務など細かく聞かれました。いろいろな数字について確認していく作業は大変ではありましたが、譲渡というゴールがあったので成し遂げることができました。
最後にインテグループに対する評価と、譲渡を検討する経営者にメッセージをお願いします。
岡部さんには誠実な対応をしてもらい、大変感謝しています。初めて会ったときから「この人なら間違いない」と思い、最後まで頼ることができました。
事業の先行きについて悩んでいる経営者には、M&Aという選択肢を考えることをおすすめします。事業の縮小や廃業は、顧客や取引先、従業員に迷惑をかけてしまうリスクがあります。それよりも、会社を引き継ぎ、伸ばしてもらえる企業を探すほうがいいのではないでしょうか。









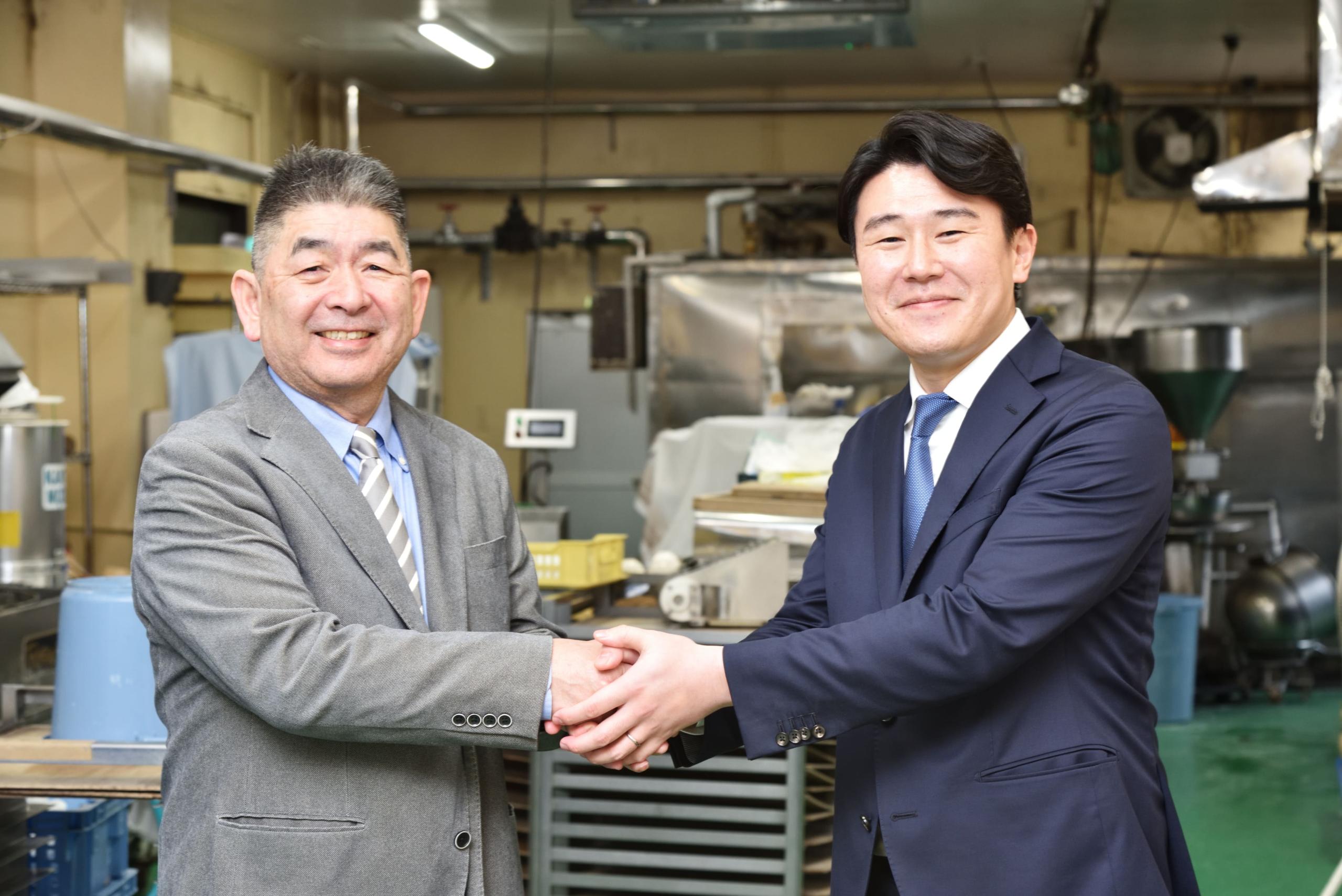
 コンサルティング部
コンサルティング部